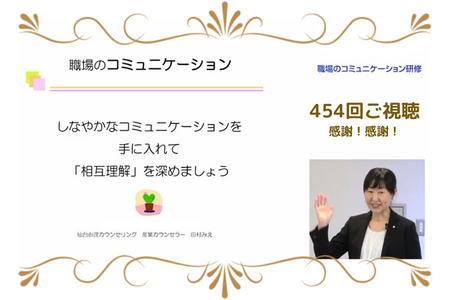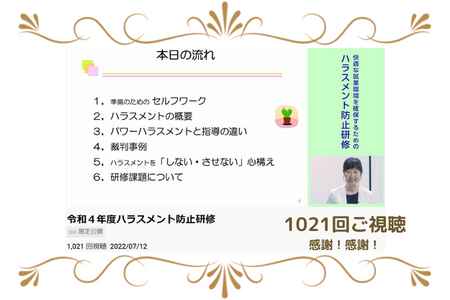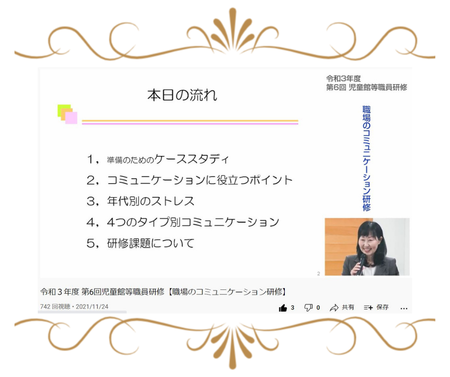アサーションとは「(さわやかな)自己表現」
自他共に尊重し自分の意見を表現する事。

◆アサーション(assertion)とは
アサーションとは「(さわやかな)自己表現」。自他共に尊重し自分の意見を表現する事。アサーティブな方法とは「自分の気持ちや考えを相手に伝えるが、相手のことも配慮するやり方」自分も相手も大切にしたやり方です。
1:アサーション(assertion) 度 チェックリスト
・自分から働きかける言動 (はい○ いいえ×)
□ 1、あなたは誰かにいい感じを持った時その気持ちを表現できますか。
□ 2、あなたは自分の長所や成し遂げたことを人に言うことができますか。
□ 3、あなたは自分が神経質になっていたり緊張している時、
それを受け入れる(認める)ことができますか。
□ 4、あなたは見知らぬ人たちの会話の中に気楽にはいっていくことができますか。
□ 5、あなたは会話の場から立ち去ったり、別れを言ったりすることができますか。
□ 6、あなたは自分が知らない事やわからない事があった時、
その事について説明を求めることが出来ますか。
□ 7、あなたは人に援助を求めることができますか。
□ 8、あなたが人と異なった意見や感じを持っている時、それを表現することができますか。
□ 9、あなたは自分が間違っている時、それを認めることができますか。
□ 10、あなたは適切な批判を述べることができますか。

2:アサーション(assertion) 度 チェックリスト
・人に対応する言動 (はい○ いいえ×)
□ 11、人から褒められた時、素直に対応できますか。
□ 12、あなたの行為を批判されたとき受け応えができますか。
□ 13、あなたに対する不当な要求を拒むことができますか。
□ 14、長電話や長話の時、あなたは自分から切る提案をすることができますか。
□ 15、あなたの話を中断して話し出た人に、そのことを言えますか。
□ 16、あなたはパーティや催しものへの招待を、受けたり断ったりできますか。
□ 17、押し売り(強引な誘い)を断れますか。
□ 18、あなたが注文した通りのもの(料理や洋服など)が来なかった時、
そのことを言って交渉できますか。
□ 19、あなたに対する人の好意がわずらわしい時、断ることができますか。
□ 20、あなたが援助や助言を求められた時、必要であれば断ることができますか。
●あなたのアサーション度チェック集計(はい○ いいえ×)
○の数 → ( /20) 個
×の数 → ( /20) 個
◆エクササイズ
アサーション度チェック項目で、「はい」の数はいくつあったでしょうか。「はい」が半分以上あれば、アサーション度は高めということになります。「いいえ」と答えた項目は、自已表現が苦手な領域と言えます。「はい」と答えた項目についても、その相手に対して否定的な感情を伴ったものであれば、相手に配慮していない発言である可能性があります。アサーションを実践していく上で、「どんな点に注意したら良いか」、自分の特徴、ポイント等を、ご自身でまとめましょう。
◆アサーション(assertion) →「(さわやかな)自己表現」:自他共に尊重し自分の意見を表現する事。
アサーティブな方法とは「自分の気持ちや考えを相手に伝えるが、相手のことも配慮するやり方」自分も相手も大切にしたやり方です。アサーティブな自己表現では自分の気持ち、考え、信念に対して正直・率直に、また、その場にふさわしい方法で表現します。しかし、どんなにアサーティブに表現したとしても、それが相手に受け入れてもらえるとは限りません。
お互いが率直な意見を出し合えば、相手の意見に賛同できないことも出てくるでしょう。そのときに、攻撃的に相手を打ち負かしたり、非主張的に相手に合わせたりするのではなく、お互いが歩み寄って一番いい妥協点を探ることがアサーティブなあり方であると言えます。

◆アサーティブになる第一歩
どんなときにも攻撃的な方法での表現しかできない人や、非主張的な表現しかできない人もいます。また、友人など気心が知れた人に対してはアサーティブでいられるのに、親や上司など立場が上の人に対してはいつも非主張的になってしまったり、子どもや部下など立場が下の人に対しては攻撃的になってしまうなど、状況によってアサーティブな表現ができない人もいます。常に攻撃的・非主張的な人も、状況によってそうなってしまう人も、まずは自分がどのようなときにアサーティブでない態度を取ってしまうのかを振り返ってみましょう。そこから、アサーティブになるための第一歩が始まります。
※アサーション・トレーニング及び自己表現力UPをご希望の皆様には、「オフィスカウンセラー講座」初級編(80分×全3回)と「オフィスカウンセラー講座」中級編(80分×全3回)がお勧めです。ご興味のある方は、是非、ぜひ!メールにてお問い合わせ下さい。お待ち申し上げております。
*
※参考文献「アサーション・トレーニング」
さわやかな<自己表現>のために
平木 典子/著 日本・精神技術研究所2021.7
関連リンク
◆【学校における一次・二次・三次的援助サービス】
◆【SOC理論 選択的最適化理論 バルテス】
◆【アサーションチェックリスト 自己表現】
◆【ソクラテス問答法 認知行動療法】
◆【タイプA型行動パターン フリードマン】
◆【タイプa型行動パターンとタイプA型行動チェック】
◆【無意識(潜在意識)と意識(顕在意識)】
◆【原因帰属理論 ワイナー】
認知行動療法関連リンク
◆仙台の認知行動療法|HSPにも効果的な認知行動療法
◆仙台の認知行動療法|心理カウンセラー養成講座中級編
◆行動療法|スキナー
◆認知行動理論|認知療法
◆認知行動理論|自動思考スキーマ